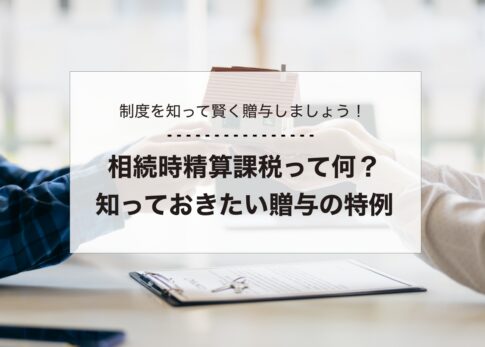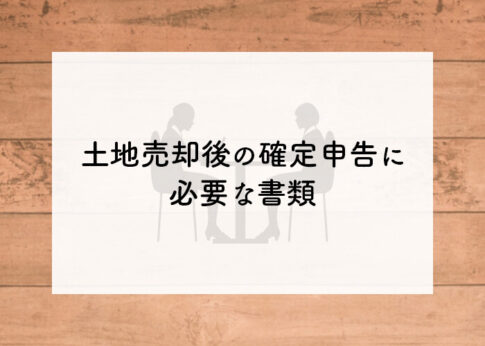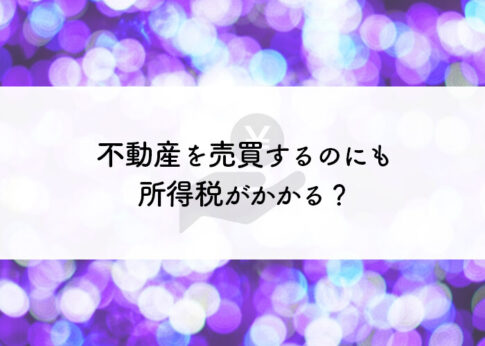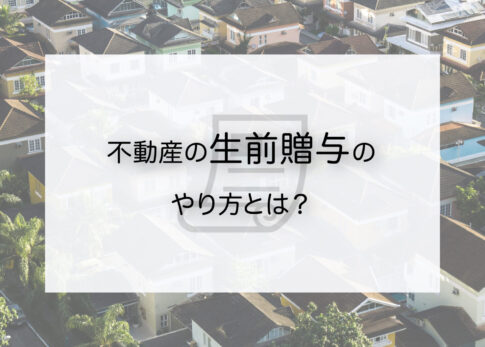相続税や贈与税でお困りの方は多いのではないでしょうか。
相続税や贈与税には各々配偶者控除という制度があり、節税できる仕組みがあります。
そのうち、今回は贈与税の配偶者控除である「おしどり贈与」についてご紹介します。
メリット・デメリットや注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

Contents
□婚姻してから20年以上の夫婦が不動産を贈与したときの贈与税の制度とは?
みなさんは「おしどり贈与」というものをご存じでしょうか。
おしどり贈与とは、「贈与税の配偶者控除」です。
婚姻してから20年以上経っている夫婦間に認められている優遇制度です。
細かく解説しますと、マイホームである居住用不動産か居住不動産を購入するためのお金を夫婦間で贈与する場合、2,000万円までであれば贈与税がかからないという制度です。
また、贈与税には、年間110万円の基礎控除があります。
そのため、1年間の中で他に贈与を受けていない場合は、合わせて2,110万円まで贈与税はかからないということになるのです。
なぜ、婚姻してから20年以上が経っている夫婦におしどり贈与という制度が定められているのか、疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。
その理由を解説します。
前提として、どんなに仲が良い夫婦や親子でも、お金や不動産などの財産のやり取りをすると贈与という位置付けになります。
そのため、年間110万円以上の財産を受け取った人は、翌年3月15日までに確定申告をし、贈与税を納める必要があります。
しかし、夫が妻に渡す生活費や親が子供のために使う教育費などにも贈与税がかかると、大変困りますよね。
このような理由で、生活する上で必要なもののやり取りには基本的に贈与税がかかりません。
□おしどり贈与のメリット・デメリット
おしどり贈与を適用する方は、メリット・デメリットを理解しておく必要があります。
それぞれ解説しますので、参考にしてください。
*メリット
メリットは、1人の人が持つ財産を配偶者に分けることで相続税の節税ができることです。
例えば、夫婦で持つ財産のほとんどを夫が保有しているとします。
そのときに夫が先に亡くなった場合、妻が夫の財産を相続するときに相続税がかかる場合があります。
この際、おしどり贈与を使って居住用不動産を部分的に妻に移しておくことで、相続税が発生しない状態にできる可能性があります。
*デメリット
一方、デメリットは、不動産所得税や登録免許税は非課税の対象にはならないことです。
おしどり贈与は、贈与税に関しては2,000万円までは非課税になりますが、不動産所得税や登録免許税は非課税の対象にはなりません。
不動産を相続した場合には、不動産取得税が非課税になります。
一方で、贈与の場合は固定資産税評価額の4パーセントが発生してしまいます。
登録免許税も相続の場合は0.4パーセント、贈与の場合は2パーセントになるので、税の負担は5倍にもなってしまいます。
また、おしどり贈与を適用し、受け取った人が先に亡くなってしまった場合、逆に相続税が増えてしまうことになります。
それだけでなく、おしどり贈与を使わなければ相続税が発生しなかったのにもかかわらず、利用したことによって相続税が発生する可能性もあります。
夫婦のどちらが先に亡くなるかは分からないので、それが分からない限り、おしどり贈与を使うメリットが絶対にあるとは言い切れません。
□おしどり贈与をする上での注意点
これまでおしどり贈与のメリットやデメリットをお話ししました。
ここでは、おしどり贈与の注意点をご紹介します。
1つ目は、贈与税の申告書を提出することです。
当然のことですが、おしどり贈与を利用する場合は贈与税の申告書を提出することが決まっています。
相続の特例を利用するときも同じですが、特例を利用して計算した結果、税金がかからないことが判明したので申告しなかったという人がいらっしゃいます。
しかし、特例を利用する場合は必ず申告をする必要があります。
贈与税が発生しないからといって安心せずに、申告書を提出するのを忘れないようにしましょう。
2つ目は、おしどり贈与の利用は1度だけだということです。
おしどり贈与が利用できるのは、同一の配偶者間で1度だけです。
「同一の」という言葉が重要です。
そのため、同一の相手ではない場合は、2回以上使用できます。
例えば、1人目の妻におしどり贈与をしてから離婚しても、2回目の結婚で前とは違う人におしどり贈与ができます。
このときも、婚姻してから20年以上経っていることが条件なので期間を満たしている必要があります。
おしどり贈与は1人につき一生に1度だけ利用できるものなので、今後の人生設計も考慮してタイミングを考えましょう。

□まとめ
今回は、おしどり贈与についてご紹介しました。
おしどり贈与は、税金がかかることなく2,000万円の財産を贈与できる制度です。
しかし、必ずしも全員にメリットがある制度だとは限らないので、ご自身の状況をしっかり見極めながら利用するかどうか判断しましょう。